学科試験を合格すると息もつかぬ間に始まる製図試験。
製図試験では、図面作成や計画の要点の記述が主な出題内容です。
試験時間6時間30分のなかで、課題に沿った建物を設計し、図面を手書きし、計画の要点を記述するという、ハードかつタイトなスケジュールとなっています。
本記事では製図試験に合格するうえで意識すべき2つのポイントをお話しします。
要点記述対策ははじめに終わらせる
要点記述とは
要点記述とは、図面内容を補足する位置づけで、自分の設計内容をアピールする場です。
試験時間6時間半のなかで1時間程度を使って記述を行う方が多いです。
採点の配分は非公開ですが、とある資格学校では、全体の4割を要点記述が占めるという見方をしています。
しかし重要性の高さの一方で、初めて受験される方は、エスキスや作図の対策に時間を追われ、記述対策が後回しになることも少なくないのではないでしょうか。
対策を急ぐ理由
要点記述の目的は、計画内容をアピールすることです。
逆に言えば要点記述の模範解答を学習することで、計画する上での要点をつかむことができます。
特に初学者や普段設計業務を行わない方は、はじめエスキスに苦労することと思います。
どこから手をつかていいかわからないところからのはじめの一歩としても、要点記述対策ははじめに終わらせることは有効です。
普段設計を行う方でも、自分の専門外の分野(意匠設計者であれば構造・設備)の計画ではどのようなものが良しとされるのか、はじめに把握しておくことで、合格図面を作成できるようになるまでの道筋は近くなると思います。
構造設計者、設備設計者も然りです。
実際に私は8月中旬には、記述で困ることがない状態にはしていました。
要点記述の具体的な勉強方法やコツはこちらをご覧ください。
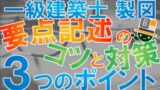
主体的に情報収集する
特定の講師・学校に依存しない
自分の担当講師を信用しすぎるのは禁物です。
製図試験は採点基準が公開されていないため、同じ資格学校内の講師でも言うことが異なる場合があります。
私は某大手資格学校の短期コースに通っていましたが、担当講師が頼りなかったので、自分で情報収集することにかなり力を入れていました。
知人が自分と異なる資格学校に通っている場合は、よく会話すると良いと思います。
自分が知らない採点基準をもっていることがあります。
また、まだ資格学校を決めていない場合は敢えて知人と異なる学校に通うことをおすすめします。
他学校の教材を入手できる場合は、入手しましょう。
実際に問題を解く時間がなくても、解答解説を見るだけでと自分の資格学校との作図ルールにおける違いがわかります。
また、採点基準を設けている資格学校であれば、採点基準の違いも参考になります。
私は4つの資格学校の問題・解答を集め、違いがあれば、全資格学校の安全側で作図するようにしていました。
つまり、ある学校では記載不要、ある学校では記載要としている場合は、記載する方を採用するということです。
独学合格も可能
私は資格学校に通いましたが、独学で合格される方もいます。
私が通っていた資格学校は、当日課題1枚、宿題1枚の計2枚を1週間でこなすサイクルでした。
その際、大勢の生徒の回答を爆速で採点している講師に添削してもらうよりも、自分で模範解答と照らし合わせて採点するほうが見落としがなく勉強になるように感じました。
私は学科独学合格後、悩んだ末、製図は資格学校に通うことを決めましたが、何らかの方法で教材を入手できるのであれば、独学も合理的な判断かと思います。
要点ノート
以上、製図試験について、製図試験に合格するうえで意識すべき2つのポイントを記しました。
最後に本ページの要点をまとめておきます。
要点ノート
要点記述対策ははじめに終わらせる
早期に記述をマスターすることで、エスキス力アップにつながる
主体的に情報収集する
採点基準が不明瞭な製図試験に対応するため、積極的に情報収集し、見えない採点基準を満たすための努力をする
📋 試験当日の作業順に不安がある方へ
製図試験は「設計力」だけでなく「時間管理力」が問われる試験です。
限られた6時間30分の中で、どの順番で何を進めるか——それが合否を分けることもあります。
そこで私自身の受験経験をもとに、試験当日の作業順を1枚にまとめた「作業順チェックリスト(PDF)」も作成しました。
各ステップの目的・注意点・整合性チェックのタイミングなどを1枚にまとめた実践ツールです。
記述のコツや、あと一歩で落ちないためのテクニックも収録。
Ken-Shiraでは、記述対策テンプレートや教材レビュー表など、受験戦略に役立つ資料も展開しています。
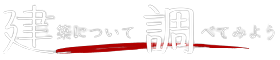
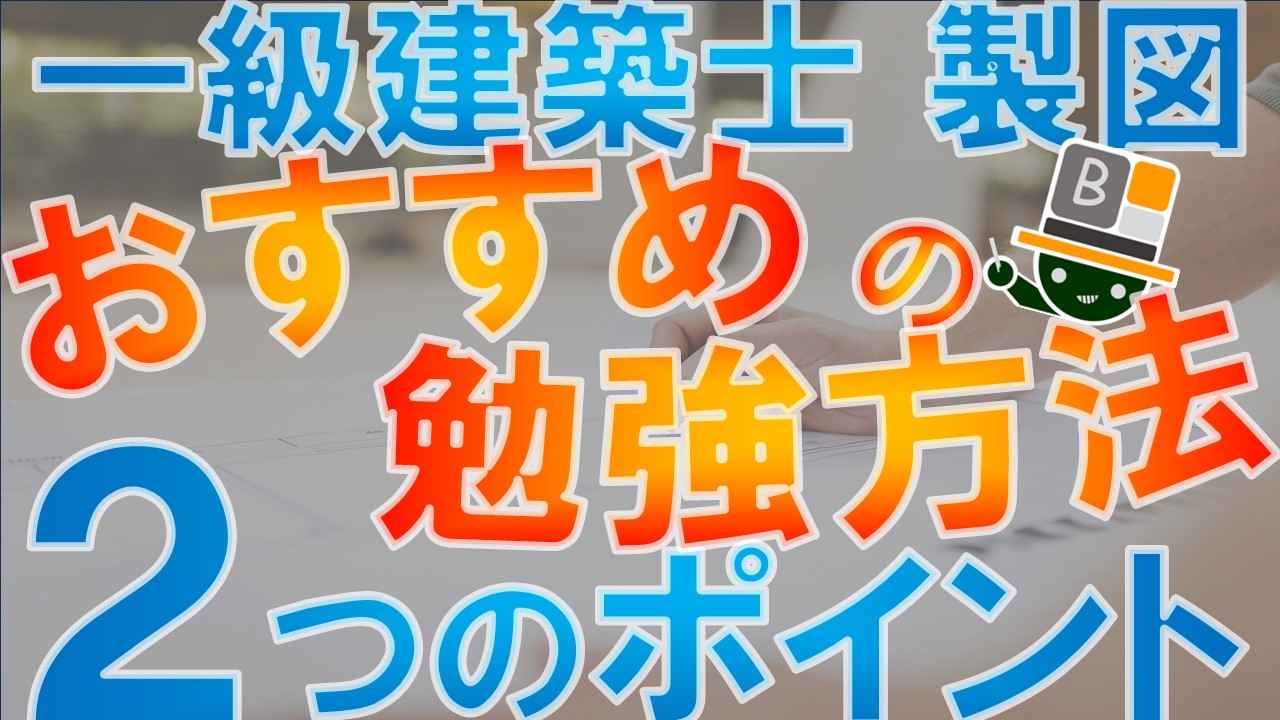
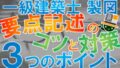
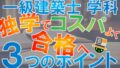
コメント