住宅セーフティネット制度を平たく説明すると、高齢者や障害者、外国人、子育て世帯等の住宅の確保に配慮が必要な方々へ、最低限の住宅供給を保証する制度です。
一つずつ紐解いて説明していきます。
住宅セーフティネット制度とは?
なぜ制定されたのか
近年、高齢者や障害者、外国人、子育て世帯等の住宅の確保に困難を抱えた方々が増加傾向にあります。
一方で、人口減少により民間の空き家や空室は増加している状況があります。
そこで、これらを合わせて解決するために、住宅セーフティネット制度が2017年10月から開始しました。
3つのキーワード
住宅セーフティネット制度は、以下の3つのキーワードで成り立っています。
- 「住宅確保要配慮者の入居を拒まない賃貸住宅の登録制度」 = 貸す部屋の確保
- 「登録住宅の改修や入居者への経済的な支援」 = 貸出の促進
- 「住宅確保要配慮者に対する居住支援」 = 入居の促進
以降、この3つのキーワードについて一つずつ解説していきます。
「住宅確保要配慮者の入居を拒まない賃貸住宅の登録制度」について
だれがどこに登録する制度?
この登録制度は住宅セーフティネット制度におけるベースとなります。
ここでいう登録とは、 賃貸人(賃貸住宅の持ち主≒大家さん)が、住宅確保要配慮者の入居を拒まない賃貸住宅を、自治体(都道府県、政令市、中核市等)に登録をすることを言います。
ここで登録された住宅が、セーフティネット住宅と呼ばれ、住宅の確保に困難を抱えた方々に供給されるわけです。
住宅確保要配慮者とは誰のこと?
登録住宅に入居するには住宅確保要配慮者である必要があります。
住宅確保要配慮者とは、月収 15.8万円以下の低額所得者、発災から3年以内の被災者、高齢者、障害者、子供が高校生相当以下の子育て世帯、外国人等を指します。
これらは、法律や省令、計画(自治体が作成する供給促進計画)にて定められたものです。
「登録住宅の改修や入居者への経済的な支援」について
前文では、住宅確保要配慮者への供給する住宅を確保するための登録制度があることを説明しました。
しかし、せっかく登録制度をつくっても、実際に登録してくれる賃貸人がいなければ意味がありません。
そこで、住宅セーフティネット制度には、賃貸人に対する2つの経済的支援があります。
- 改修に対する支援措置
- 低額所得者が入居する際の負担を軽減するための支援措置
改修に対する支援措置
一つ目は改修に対する支援措置です。
- 耐震改修
- 間取り変更
- シェアハウスへの改修
- バリアフリー改修
- 居住のために最低限必要と認められた工事
- 居住支援協議会等が必要と認める工事
- これらに係る調査設計計画の作成
限度額等の条件はありますが、上記のような改修や工事を対象に経済的支援を設けることで貸す側の負担を軽くし、登録住宅を増やそうというわけです。
低額所得者が入居する際の負担を軽減するための支援措置
二つ目は、低額所得者が入居する際の負担を軽減するための支援措置です。
入居者が低額所得者である場合には、家賃滞納のリスクがあります。
そのため、賃貸人としては、低額所得者の受け入れに抵抗があるのも当然です。
そこで、低額所得者が入居する際の負担を軽減するための以下の支援措置が設けられています。
- 「家賃低廉化への補助」
- 「家賃債務保証料低廉化への補助」
「家賃低廉化への補助」は、低額所得者が入居する際に、入居者の負担を低減するために家賃を下げた場合、その家賃減額分に対して、1戸あたり毎月最大4万円の補助を受けられるというものです。
「家賃債務保証料低廉化への補助」は、低額所得者が入居する際に、入居者の負担を低減するために初回の保証料を下げた場合、その減額分に対して、最大6万円の補助を受けられるというものです。
ただし、両者を併用する場合、1戸あたり1年間の両補助金の合計額の上限は48万円となっています。
上限が設けられているものの、賃貸人にとってはメリットの大きい制度といえます。
また同時に、入居者への経済的支援の役割も持ちます。
改修に対する支援措置は主に貸す側に対するメリットを考えたものでしたが、低額所得者が入居する際の負担を軽減するための支援措置は、貸す側だけでなく借りる側にとってもメリットのある制度といえます。
「住宅確保要配慮者に対する居住支援」について
これまで説明したような制度があっても、実際に困難を抱えている住宅確保要配慮者が、その存在を知らなければ、入居方法がわからなければ、意味がありません。
そこで要配慮者の登録住宅への入居支援を目的として、主に以下の2つの団体により措置が設けられています。
- 居住支援協議会
- 居住支援法人
居住支援協議会は、不動産関係団体、居住支援団体、地方公共団体等で構成されます。
居住支援法人は、都道府県知事が指定する、NPO法人・一般社団法人・一般財団法人・社会福祉法人等を指します。
これらの団体は、住宅確保要配慮者の円滑な入居を目的として、情報提供・入居相談等の各種居住支援を行います。
要点ノート
以上、住宅セーフティネット制度について、周辺情報とともに解説してきました。
最後に本ページの要点をまとめておきます。
要点ノート
1. 住宅セーフティネット制度とは?
人口減少による空き家増加 & 住宅確保要配慮者の増加
→住宅セーフティネット制度をつくり、3つのキーワード(2,3,4)で要配慮者に住宅供給
2. 住宅確保要配慮者の入居を拒まない賃貸住宅の登録制度とは?
要配慮者に供給する住宅を確保しよう
→登録制度が必要
3. 登録住宅の改修や入居者への経済的な支援とは?
登録してもらえる賃貸住宅を増やそう
→改修への補助 & 家賃低廉化への補助
4.住宅確保要配慮者に対する居住支援とは?
入居者を増やそう
→居住支援協議会、居住支援法人による情報提供や相談
参考:国土交通省
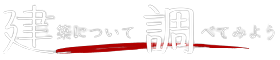
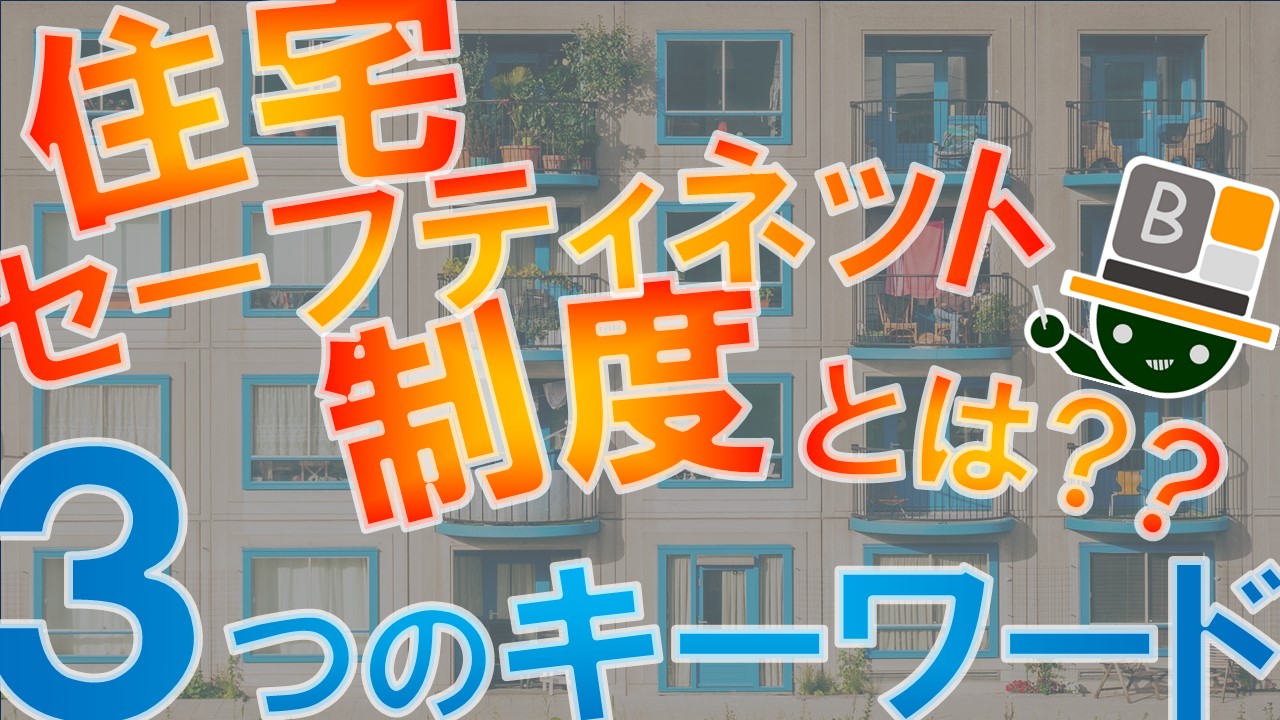
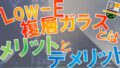
コメント