一級建築士製図試験において、対策が遅れがちになるのが、要点記述問題かと思います。
初めて受験される方は、エスキスや作図の対策に時間を追われ、記述対策が後回しになることも少なくないのではないでしょうか。
本記事では、記述対策の重要性を説明するとともに、その対策やコツについて、お話します。
要点記述対策は重要
要点記述の得点配分は不明ですが、某資格学校では製図試験全体の4割とも言われています。
よって、成果物として図面がメインといえど、記述問題の重要性を無視することはできません。
また要点記述が自身の計画内容を補足するものであることからも、記述対策がそのままエスキス対策にもなると考えます。
私は普段エスキスを行うような業務は行っていなかったものですから、好ましい計画がどのようなものかを把握するためのはじめの一歩としても有効でした。
要点記述のコツ
文章ではなく文節で暗記する
記述内容を暗記するといっても限度があります。
特に製図試験は学科試験と異なり、勉強スケジュールがタイトです。
そこで、暗記を効率化するために「主語」「述語」「理由」の3つの文節に分けて組み合わせで覚えることを推奨します。
3つの文節に分けて勉強することで、暗記量を必要最小限にとどめることができ、また全体像を整理することが可能です。
自分のフォーマットを固める
限られた試験時間のなかで素早く文章を構築するために、自分の文章構成をもっておくことが大事です。
私は前項でお話した「主語」「述語」「理由」の3つの文節をこの順で「主語」→「述語」→「理由」と並べて記述していました。
- 主語:○○は
- 述語:△△に配置し
- 理由:□□に配慮した
私は上記のフォーマットを使っていましたが、自分のフォーマットを固めておけば、語順は好みで入れ替えても差し支えないと思います。
また、私は某大手資格学校に通っていましたが、資格学校テキストでは例文が羅列しているだけで、勉強しにくかった印象です。
よって記述問題については市販参考書を併用するとスムーズに勉強が進められると考えます。
参考までに、下記に私が使用していた参考書の最新版を掲載します。
製図試験全般を対象にした参考書ですが、後半部分に記述対策について書かれており、テーマごとに「主語」「述語」「理由」が表で分けて整理されているので、初学者には特におすすめです。
図面との整合性をとる
前項までの暗記である程度の記述には戦えるようになります。
ただし、図面との整合性がとれていないと大幅減点の可能性が高いです。
ある程度図面を完成させられるようになってくると見直しの時間を設けられるようになります。
自分の見直しチェックリストのなかに記述と図面との整合性チェックを入れておくことをおすすめします。
また、記述内容はエスキスと並行して考えておくと、ミスをさらに減らすことができます。
私は本番でうまくいったものの、それまでの模試はここでのミスが頻発していましたので、ここで注意喚起させていただきます。
採点基準は採点者基準
採点者も人間のため、採点者の主観で得点が左右する可能性があることを意識すべきです。
- 採点者に対するアピールであることを意識する
- 意味が伝わればいいというものではなく、見栄えや文章の美しさにも留意する
- 短文で簡潔な文章を心がける
上記の考え方は作図でも同様と思われます。
学科のマーク試験とは異なり、正解不正解の境界が明確ではないため、表面的で配慮のない回答でははじかれる可能性があります。
回答の先に採点者を想像して記述することが大切です。
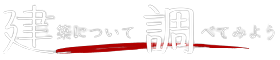
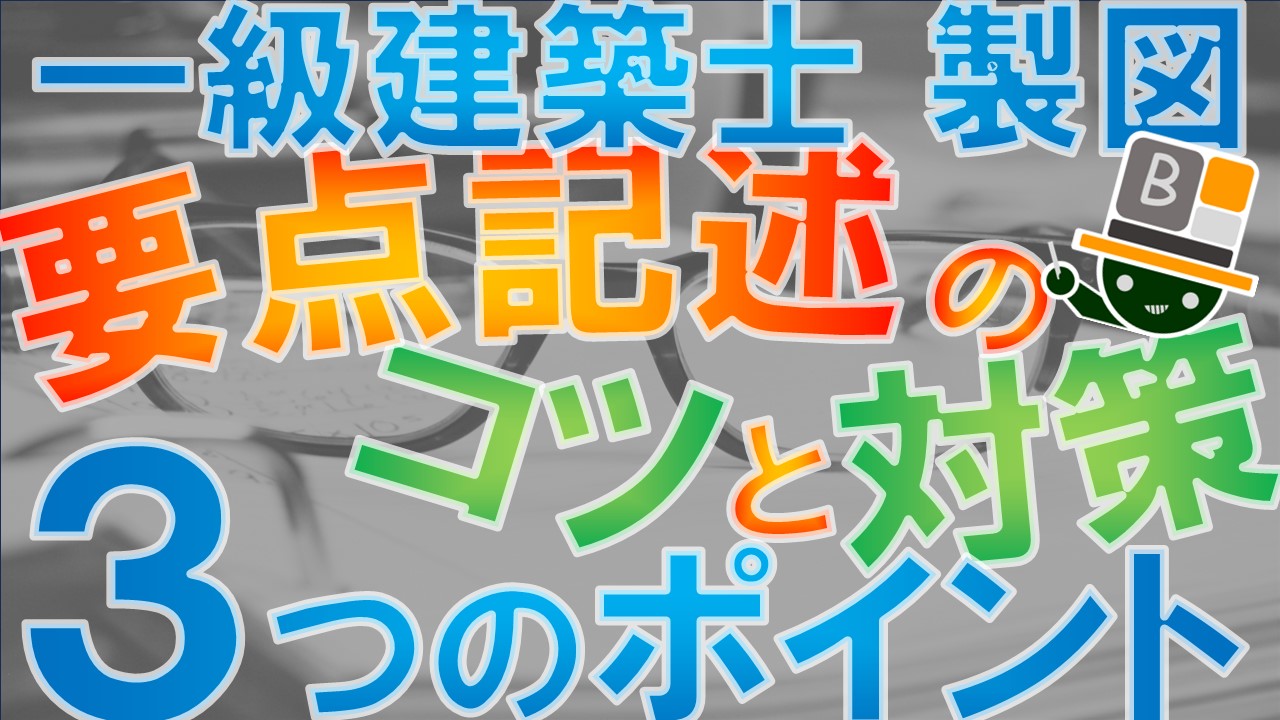

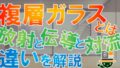
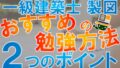
コメント