物件探しをしていると、「広さ」「築年数」「駅距離」などの条件に目が行きがちですが、本当に住みやすいかどうかは、間取りや設備の配置、そして将来の暮らし方まで含めて考える必要があります。
一級建築士として設備設計や住宅診断に携わる中で、「住みやすさ」を左右する要素には明確な傾向があると感じています。
今回は、住みやすい物件を選ぶために押さえておきたい3つの視点をご紹介します。
住みやすさを左右する3つの視点
① 間取りの合理性(動線・収納・家具配置)
生活動線がスムーズかどうかは、日々の快適さに直結します。
洗濯・料理・掃除などの動作がストレスなく行えるか、図面上で確認しましょう。
また、収納の位置や量も重要です。「どこに何をしまうか」まで想像できる間取りが理想です。
家具配置も見落としがちですが、柱の出っ張りや窓の位置によって、ベッドやソファがうまく収まらないこともあります。
② 設備の配置と使いやすさ(キッチン・洗面・浴室)
設備の配置が不自然だと、使いづらさを感じる場面が増えます。
たとえば、キッチンが狭すぎる、洗面所が通路の途中にある、浴室が暗いなど、図面では見えづらい部分に注意が必要です。
設備は「使う人の動き」に合わせて配置されているかを意識して見てみましょう。
③ 将来性(家族構成の変化・在宅勤務・老後)
今は一人暮らしでも、数年後には同居や在宅勤務など、暮らし方が変化する可能性があります。
「今だけ快適」ではなく、「将来も快適」な間取りを選ぶことが、長く住み続けるためのポイントです。
たとえば、ワークスペースを確保できるか、収納を増やせる余地があるかなども判断材料になります。
建築士の視点でのアドバイス
物件情報サイトでは、広さや築年数などの数値が並びますが、「住みやすさ」は数値では測れません。
図面を見ながら、動線・設備・将来性を総合的に判断することで、後悔のない物件選びが可能になります。
建築士による図面診断では、こうした視点から「住みにくさの兆候」を事前に見抜くことができます。
まとめ|長く快適に暮らすための選び方
物件選びは「条件検索」だけでなく、「暮らしのイメージ」から逆算することが大切です。
建築士の視点を取り入れることで、今も将来も快適に暮らせる住まいを選ぶことができます。
▶ 建築士による住まい診断+物件紹介はこちら
図面チェック付きで安心の住まい選びをサポートしています。仲介手数料は一律0.8カ月分。無料相談受付中です。
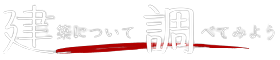
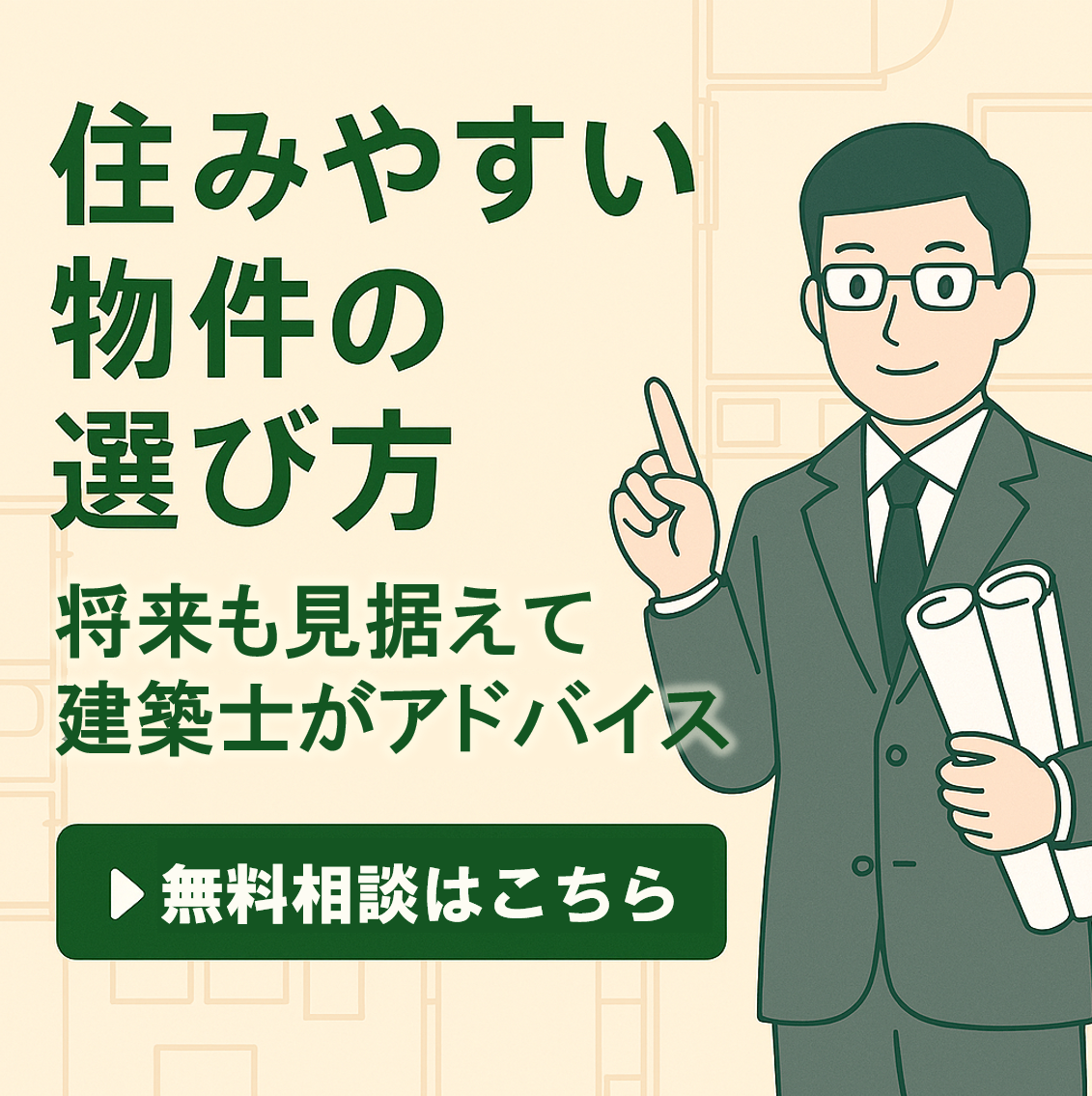
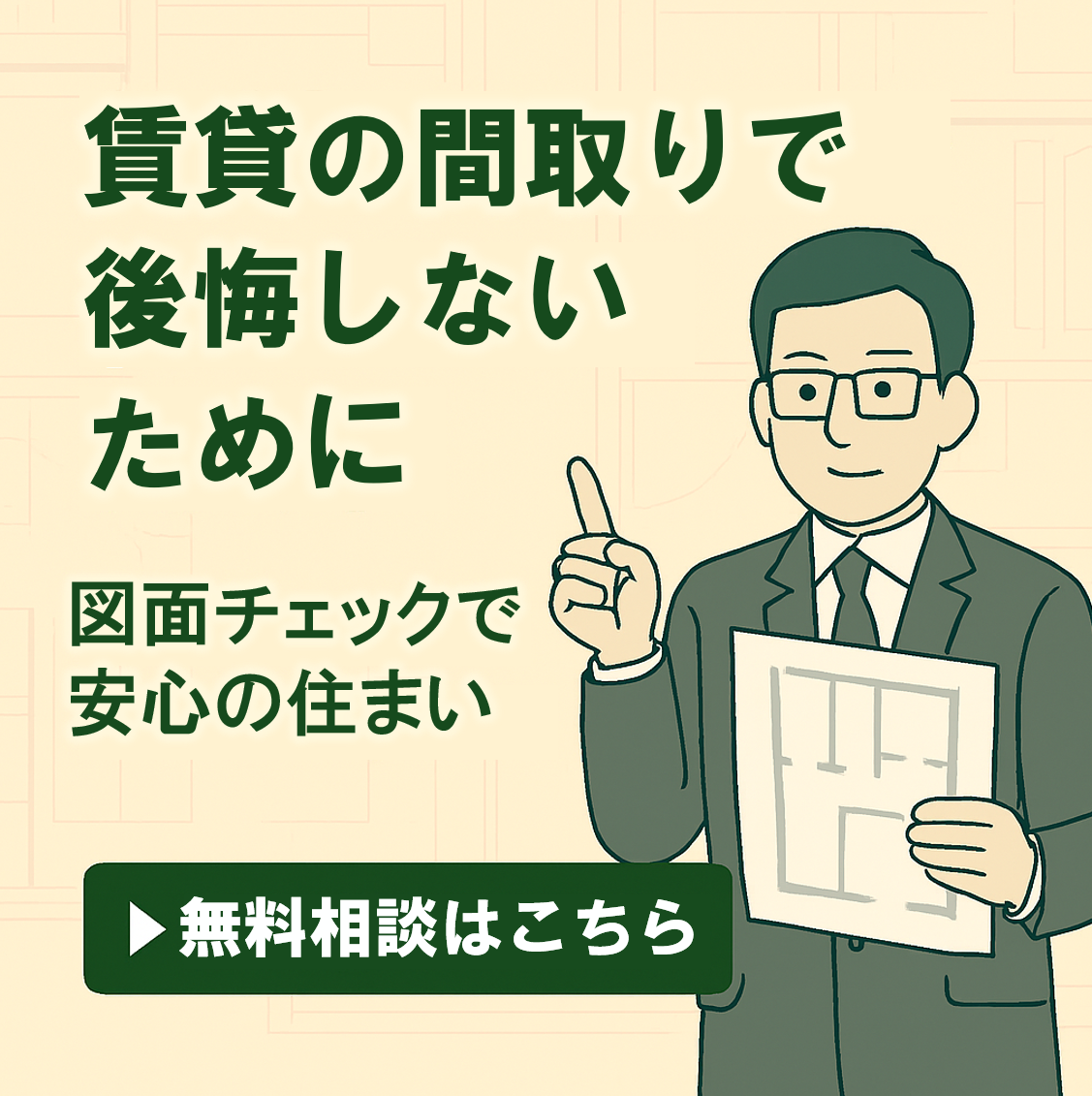
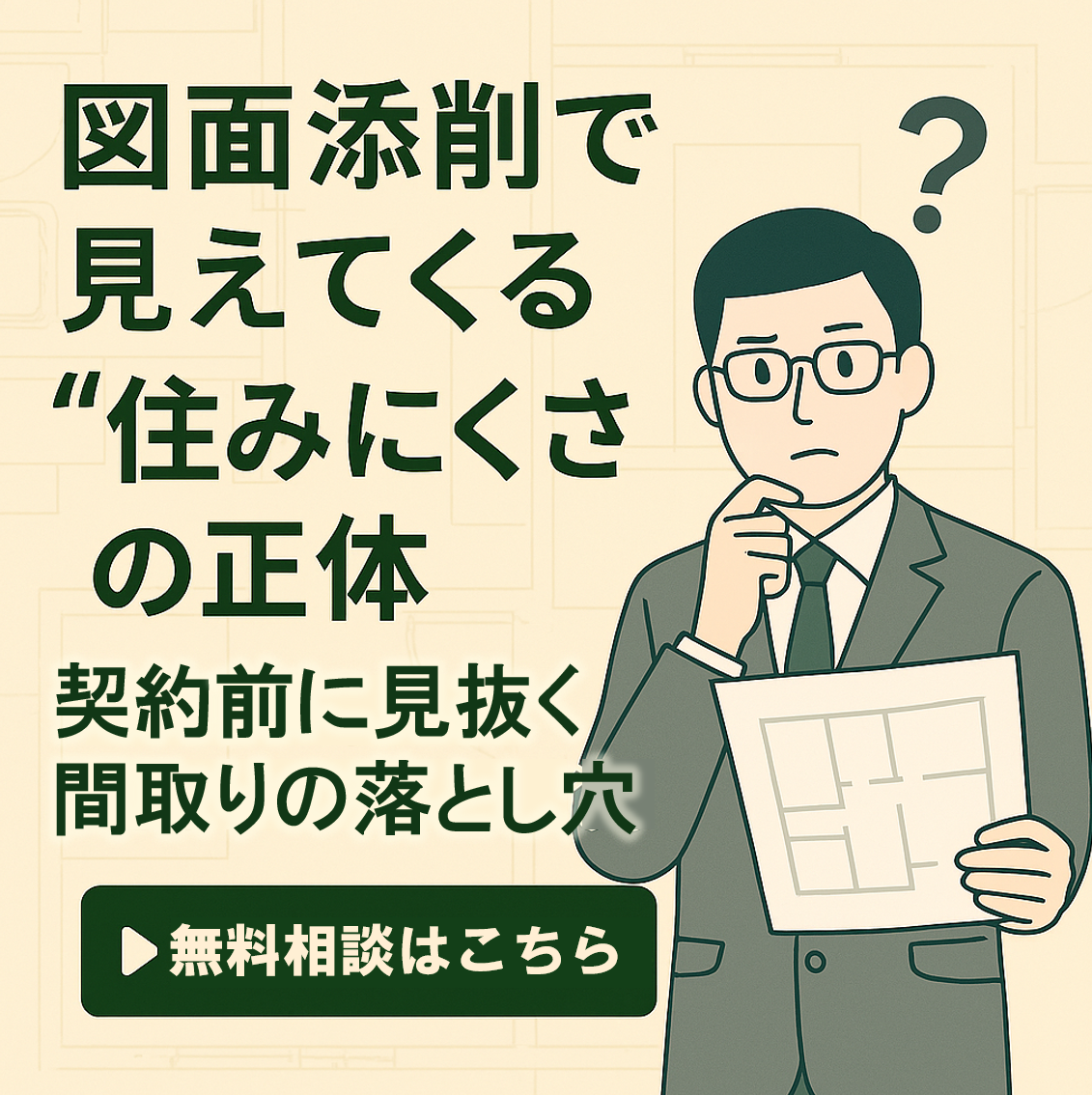
コメント